「ゾーン」は偶然ではない。トップアスリートが実践する、極限集中への入り方と9つの条件
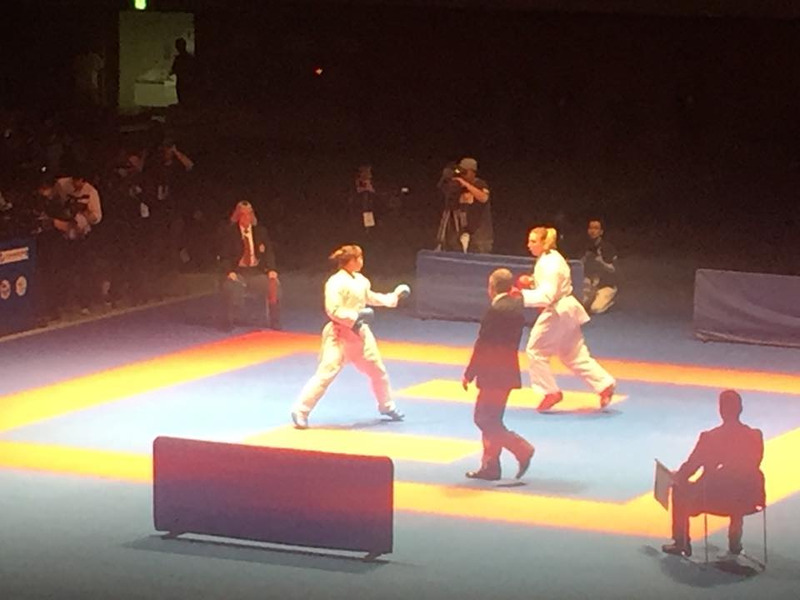
【このコラムの著者】
ゾーンとは
ゾーンとは、集中力が極限状態まで高まり、目の前の課題や作業に対して完全に没頭している状態のことです。 ゾーンの概念は「観光」「レクリエーション」「音楽活動」といったあらゆる分野で活用が期待されており、スポーツ分野においても応用することでパフォーマンス向上に役立てることが望まれています。
「ゾーン」に入ると起こること
いわゆる「ゾーンに入る」と呼ばれる状態になると、行動に対して、考えるよりも先に自然に体が反応するような感覚になります。
この状態では努力をして行動しているという感覚がほとんどなくなり、活動を行うこと自体が心地よく感じられるようになります。
また、このような状態は個人の能力と課題の難易度が釣り合っているときに起こりやすいとされています。
そのため、ゾーンに入った人は最高のパフォーマンスを発揮しやすくなるとされています。
ゾーンとフローの違い
ゾーンとフローは基本的に同じ状態を指します。
ただし、言葉を使う場面や使用される領域に違いがあります。
フローは心理学の理論用語として学術的に定義され、スポーツ以外にも仕事や芸術など幅広い分野で使われます。
一方、ゾーンは、特にスポーツ現場での実感や体験に基づいて使われることが一般的です。
なお、この記事ではゾーンをフローと同一の意味合いを持つ状態として扱っています。
アスリートがゾーンに入ると起こること
ゾーンに入ると、アスリートやスポーツ選手は高度に集中した状態になります。
ゾーンは、「集中力」や「内発的動機づけ」の融合した理想的な心理状態です。
そのため、周囲の音や視線、スコアなど、外的な環境に対しての意識が薄れ、より目の前の課題や目標に集中しやすくなります。
競技への没入が可能になった結果として、ゾーンに入ることでパフォーマンスの向上が期待できるでしょう。
具体的には、無駄のない動き、連携が取れていて洗練されたパフォーマンスなども可能になる場合があるでしょう。
また、疲労や痛みも一時的に感じにくくなることで、限界を超える力が引き出されることもあります。
このように、アスリートやスポーツ選手はゾーンに入ることで本来の実力を余すことなく発揮し高パフォーマンスを継続できるようになるでしょう。
ゾーンを構成する9つの要素
ゾーンの構成要素には以下の9つが挙げられ、これらの要素が統合して組み合わさることで生まれるとされています。
一つの要素だけでも価値のあることではありますが、特定の状況だけを意識するのではなく、それぞれの構成要素を理解することが重要でしょう。
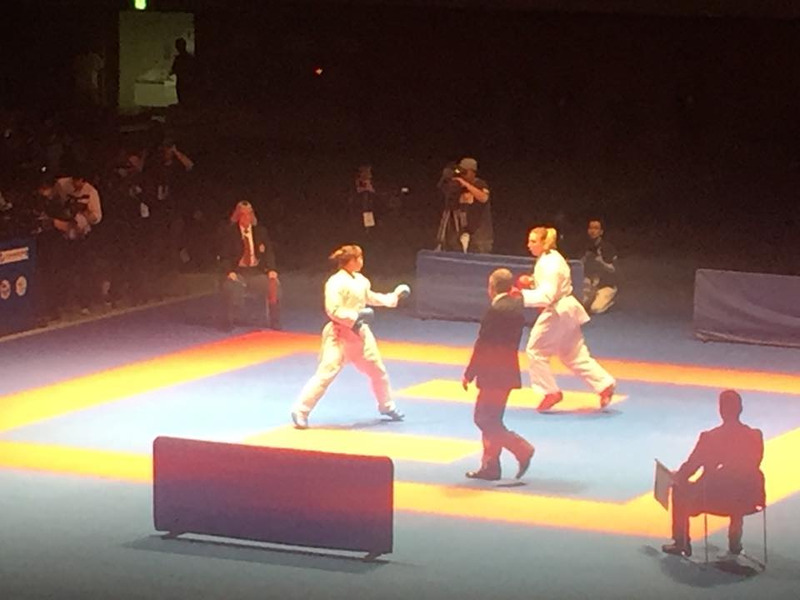
出典:https://positivepsychology.com/mihaly-csikszentmihalyi-father-of-flow/「Mihaly Csikszentmihalyi The Father of Flow」
1.挑戦と能力のバランスを均等にする
課題が自分のスキルに対して適度に難しいときにフローが起きやすいとされています。
一方、適した難易度を選択できていないと、ゾーンに入りづらく感じてしまいます。
例えば、倦怠に起因する「疲労」や「慢心」、目標を達成できないことへの「フラストレーション」「不安」といったストレスはゾーンへの妨げとなります。
そのため、適度に「手応え」を感じられると良いでしょう。
2.目標が明確になっている
何をすべきか、どこを目指しているかが明確であることも重要です。
目標が明確だと集中しやすく、迷いや戸惑いを生じにくくなるでしょう。
特にチームプレーのスポーツでは、戦術や役割が共有されていないとこの条件が満たされず、フローに入りづらくなるでしょう。
3.即座にフィードバックを行う
行動の成果がその場でわかることで、改善や調整がスムーズになります。
たとえばスポーツでは、プレーの良し悪しを即座に判断できるようになります。
目標と現状の差異を把握できるようになるとともに、目標への過程を導くことに対して集中するきっかけにもなります。
4.集中し没頭する
目の前の行動や作業以外に気を取られず、完全に目の前の活動に入り込んでいる状況のことです。
ノイズや迷いが消え集中しやすい状況になります。
特に、マルチタスクや常にあらゆる情報を認識しなければならない状況では、雑念の入りやすい状況になってしまうでしょう。
そのため、情報の分割を目的とした役割の分担を行う、などの工夫を行うことも有効かもしれません。
5.自己意識の消失
周囲の目を気にしなくなり、ただパフォーマンスを向上することだけを考えるようになります。
また自分の意識が介入しなくなることで邪念や不安といった阻害要素も消えるため、より集中することができるようになります。
6.時間感覚の変化
「時間を忘れて夢中になる」という表現はフローを体現する最も身近な表現でしょう。
また、逆に集中が高まることで時間の流れを遅く感じることもあります。
7.活動自体に内的報酬を感じる
「勝ちたい」「褒められたい」といった周囲からの評価でなく、「活動自体が楽しい」「続けていたい」と思えるような感覚のことです。
こうした状態は報酬のためではなく、行為自体が目的と化します。
8.行動と意識をリンクさせる
考えずとも体が勝手に動く感覚です。 思考と動作が同期したような状態になり、まるで”流れるような”パフォーマンスを行うことができるようになります。
熟練した競技者によく見られる特徴の一つでもあり、目にした経験のある方もいるのではないでしょうか。
9.自己をコントロールする
環境やタスクといった外的要因に振り回されるのではなく、自分が主体となって動かしている感覚を持つことです。
安心感や主体性がより集中力を高めるきっかけになるでしょう。
【最新研究から解説】アスリートがゾーンに入るために心理的不安を取り除くことが重要
スペインのムルシア大学の研究者らによって2024年に発表された論文では、14~18歳のサッカー選手328名を対象にゾーン(フロー状態)を含む競技に対する不安や自己効力感などの要因との関係を調査しました。
この研究の結果、16–18歳の選手やトップレベルの選手ほど自己効力感とフロー状態が高く、「競技不安」と呼ばれる心理的・身体的な緊張状態は低い傾向にあることがわかりました。
そのため、フロー状態の促進やパフォーマンス向上を目指す上で、競技不安を軽減するようなメンタル面での介入が成果に繋がる可能性が示唆されたと言えるでしょう。
なお、自己効力感について詳しく知りたい方は、Self-efficacy(自己効力感)は怪我の回復に関係する?をご覧ください。 この記事では自己効力感の特徴やケガとの関係についても詳しく解説しています。
出典:Analysis of the Sports Psychological Profile, Competitive Anxiety, Self-Confidence and Flow State in Young Football Players (Domínguez González etal.2024)
アスリートに対する再現性のあるゾーン状態の形成を目指そう
ゾーンやフローと呼ばれる状態は偶然生じるものではなく、心理的な条件が揃えば決して再現不可能ではないと言えるでしょう。
研究結果からもわかるようにフロー状態に入りやすい「競技不安」や「自己効力感」といった要素の状態を把握することで再現性を高めることも難しくないでしょう。
ゾーンを再現可能な経験へ変えたい方は、ぜひ専門的なメンタルコーチングの受講をおすすめします。